失語症の標準検査を始めようとしても、「右手が動かない」「視野が欠けている」──
そんな身体的ハードルに戸惑う新人 ST は少なくありません。代替アプローチの考え方の一例です。
 ホープくん
ホープくん片麻痺と視覚障害がある患者さんにSLTAを行おうとしたのですが、図版が見づらいようで、右側の指示がまったく反応されませんでした。どうすればよいですか?



SLTAは視覚が中心なので、視覚障害がある患者さんには通常通りに進めることは難しい場合が多いね。まず、図版を右寄せにして提示するか、拡大してみたかな?



それも試してみましたが、視野が大きく欠けているので、まだ反応が薄いです。指示に対する反応も遅れています。



反応が遅れても、それが「失語」の一部としての反応であれば問題ないけれど、視覚的な問題であれば、右側を常に強調して指示を出すようにすると良いかもしれないね。



なるほど、反応を引き出すために指示はなるべく簡素に、右側を中心に行ってみます。ただ、片麻痺の影響で右手が使えない場合の指示はどうしたら良いでしょうか?



そうだね、右手が使えない場合は、左手での指示を促すか、もしくは口頭での反応を強化する方法もあるよ。たとえば、「はい」や「いいえ」を声で答えてもらう形式に変えるといいかもしれないね。



口頭での反応ですね。少しでも反応を引き出す方法を見つけて試してみます。ですが、SLTAを変更せずに評価を進めるべきか迷います。



SLTAをそのまま使う場合でも、評価内容の信頼性を保つために、あくまで視覚的な配慮を最大限にすることが大切。反応形式や図版の表示方法を工夫しながら進めれば、信頼性を確保できるはずだよ。



わかりました。視覚的な工夫と口頭反応の強化を取り入れて、改めて
評価を進めてみます!
🔑 Key Point|要点整理
- Why:視覚障害や片麻痺がある患者さんにSLTAをそのまま使う場合、視覚的配慮と反応形式の調整が重要。
- How:
- 視覚障害対応:図版を右寄せ・拡大し、視野に配慮
- 反応形式の調整:遅延反応でも焦らず、口頭や音声による反応で代替
- 信頼性確保:SLTAをそのまま使う場合でも、視覚や身体的制約を考慮して進行
- Tip:反応に時間がかかる患者には焦らず、1回の反応を十分待つことが大切。急かさずリズムを保つ。



視覚障害や麻痺がある患者にSLTAを実施する際、どんな工夫をして進めていますか? コメント欄でぜひシェアしてください!
📝 Memo|参考資料
失語症検査やその解釈がわかりやすく書かれていてオススメです



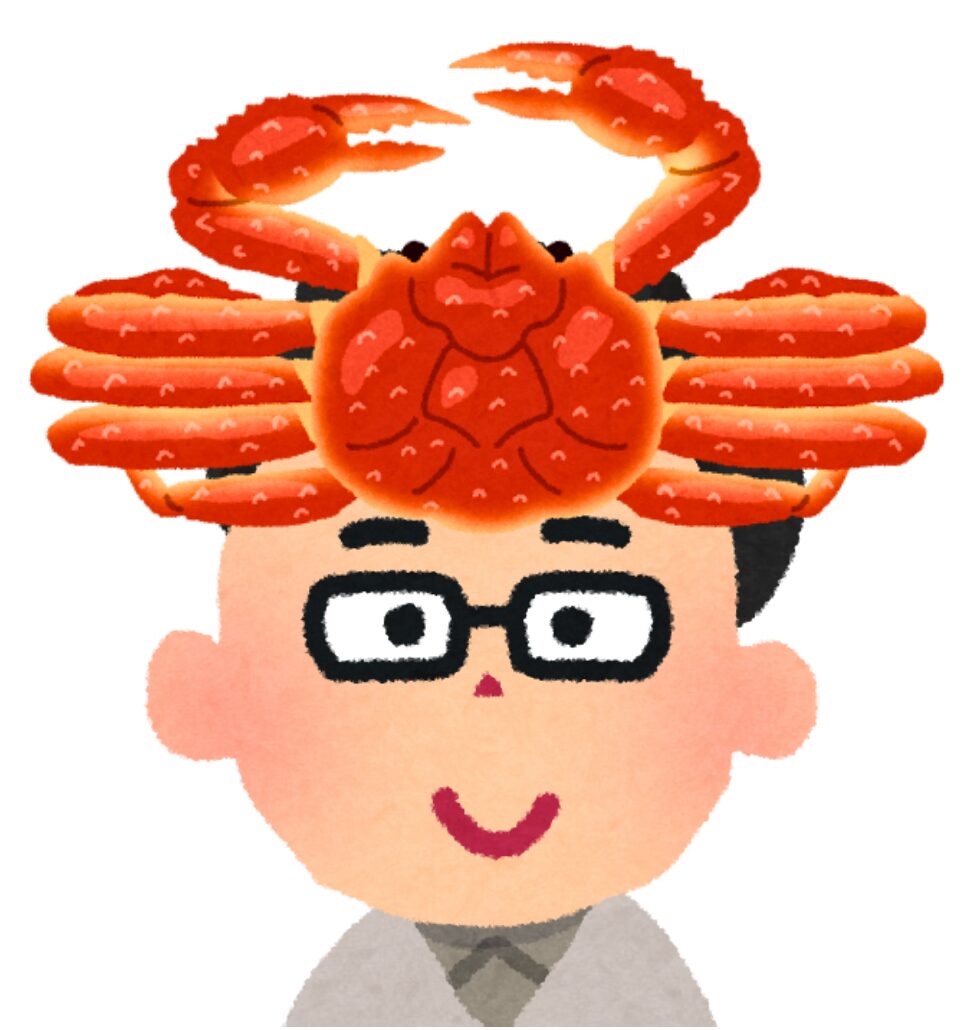
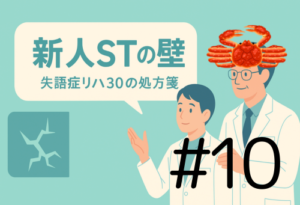







コメント