失語症の患者さんが言い間違える動詞。自動詞と他動詞が混乱しているのを見て、どう評価し、どのように支援したらいいのか迷ったことはありませんか?エラーの背景や解釈のヒントにしてください。
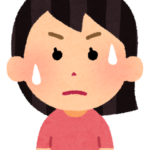 K子さん
K子さん患者さんが「座る」と言うべき場面で「座らせる」と言ったり、自動詞と他動詞が逆になることが多くて、どう解釈したらいいのか悩んでいます。



いい視点だね。そのエラーは日本語の構文的負荷が関わっていることが多いよ。
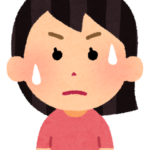
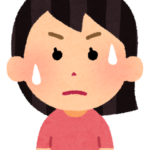
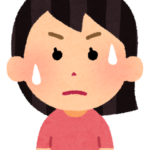
構文的負荷、ですか?



そう。自動詞は動作主体が1つだけど、他動詞は「誰が誰に何をする」という複数の要素が必要で、負荷が高いんだ。
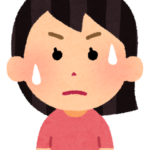
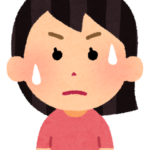
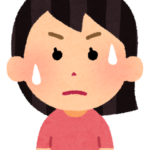
なるほど。逆に自動詞が優先されるのはその負荷の低さが関係しているんですね。



その通り。失語症のある人は負荷が軽い自動詞から出やすい。逆に他動詞に切り替わる場面でエラーが出やすい。
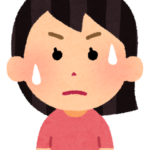
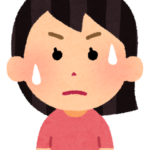
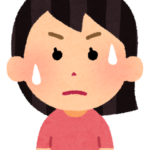
じゃあ、評価のときはどこを見ればいいですか?



「動作主体と対象の混同があるか」「他動詞の目的語が省略されているか」を観察するといいよ。



わかりました!エラーの背景にある負荷や構文の理解も意識してみます。
自動詞・他動詞のエラーは、失語症の患者さんの文産出の典型的な特徴のひとつです。日本語の特徴として、自動詞は動作主のみを表し、文の構造が単純(例:犬が走る)です。
一方、他動詞は動作主に加え、対象が必須となり(例:犬がボールを取る)、より多くの語や文構造を保持する必要があり、失語症患者にとって負荷が大きくなります。
このため、負荷が低い自動詞を優先的に使用したり、他動詞の目的語を省略したりするエラーが出やすいです。
特にブローカ失語の患者さんで顕著に見られ、単語レベルでは語彙は出るものの、文法的な処理が難しいことが背景にあります。
ポイントは以下の観察です:
- 動作主と対象の混同がないか
- 他動詞で目的語が省略されていないか
- 連鎖する動詞の選択ができているか
リハビリの際には、視覚的な支援(絵カードなど)や、対象語を提示した二択課題から練習するなど、構造の負荷を下げて訓練することが有効です。
🔑 Key Point|要点整理
- Why:自動詞と他動詞の混乱は、文法処理の負荷が原因で起こりやすい。
- How:
- 自動詞は主体のみ → 出やすい
- 他動詞は対象が必要 → 負荷が高くエラーが出やすい
- 観察ポイント → 対象が省略されていないか確認
- Tip:文を作る負荷を下げるために、視覚的ヒントや二択課題を活用する。



あなたの現場では、自動詞・他動詞のエラーをどのように観察・支援していますか?ぜひコメントでシェアしてください!
📝 Memo|おすすめの書籍



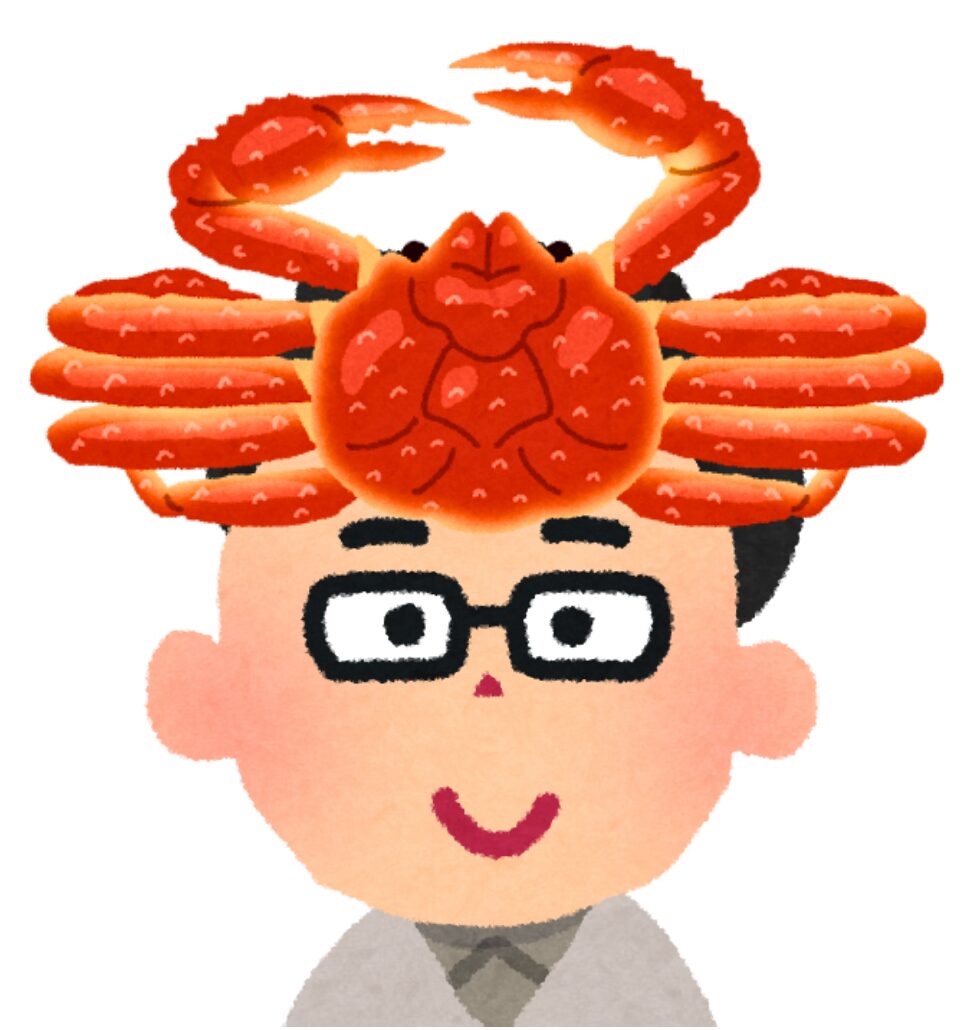
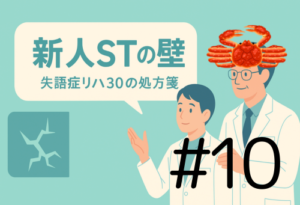







コメント