「失語症かな?」と思って検査を進めていると、口唇や舌の動きがうまくいかず、命令が通らない。でも、理解はできていそう…。──このように、オーラルアプラキシアと失語症の境界で迷う新人STは少なくありません。観察のポイントを整理しました。
 ホープくん
ホープくん患者さんが口や舌の動きの指示が全然できなくて…。失語症の理解障害なのか、オーラルアプラキシアなのか判断がつきません。



いい着眼点だね。まず確認したいのは、指示を理解できているかどうかだよ。



理解できているかどうか…具体的にはどう観察しますか?



例えば、道具の使用やジェスチャーの模倣ができているなら、言語理解は保たれている可能性が高い。理解があるのに口唇や舌の動きだけできないならオーラルアプラキシアの可能性が高い。



じゃあ、言語的な指示だけでなく、見せて真似してもらうのも重要なんですね。



その通り。言語理解が低ければ模倣も難しくなるし、非言語的な理解があるのに動作だけできないなら運動プログラムの障害(アプラキシア)だと考える。



なるほど。模倣・理解・運動の各要素を分けて観察するのがポイントですね。



そう。できれば、複数のモダリティで反応を確認してみるといいよ。
オーラルアプラキシア(口腔顔面失行)は、言語理解が保たれているにもかかわらず、随意的に口や顔の動作をうまく行えない状態です。一方、失語症の理解障害では、指示そのものが理解できず、動作につながらないケースが多いです。
| 観察ポイント | オーラルアプラキシア | 失語症の理解障害 |
|---|---|---|
| 言語理解 | 正常~軽度低下 | 明らかに低下 |
| 模倣 | できる場合が多い | 模倣も難しい場合が多い |
| 自発動作 | 可能 | 困難 |
| 道具使用 | 正常 | 困難 |
例えば、口をすぼめる、舌を出す、といった動作を見せて真似させると、理解があるかどうか、運動プログラムの問題かが見えてきます。
🔑 Key Point|要点整理
- Why:オーラルアプラキシアと失語症では訓練の焦点が異なるため、鑑別が重要。
- How:
- 言語的な指示と視覚的な模倣を両方試す
- 理解・模倣・運動の3要素を別々に確認する
- 道具使用など他の非言語的行動も観察
- Tip:真似をしてもらう際は、ゆっくり・段階的に見せると動作が出やすい。



あなたはオーラルアプラキシアと失語症の見極めで、どんな工夫をしていますか?ぜひコメントで教えてください!
📝 Memo|おすすめ書籍



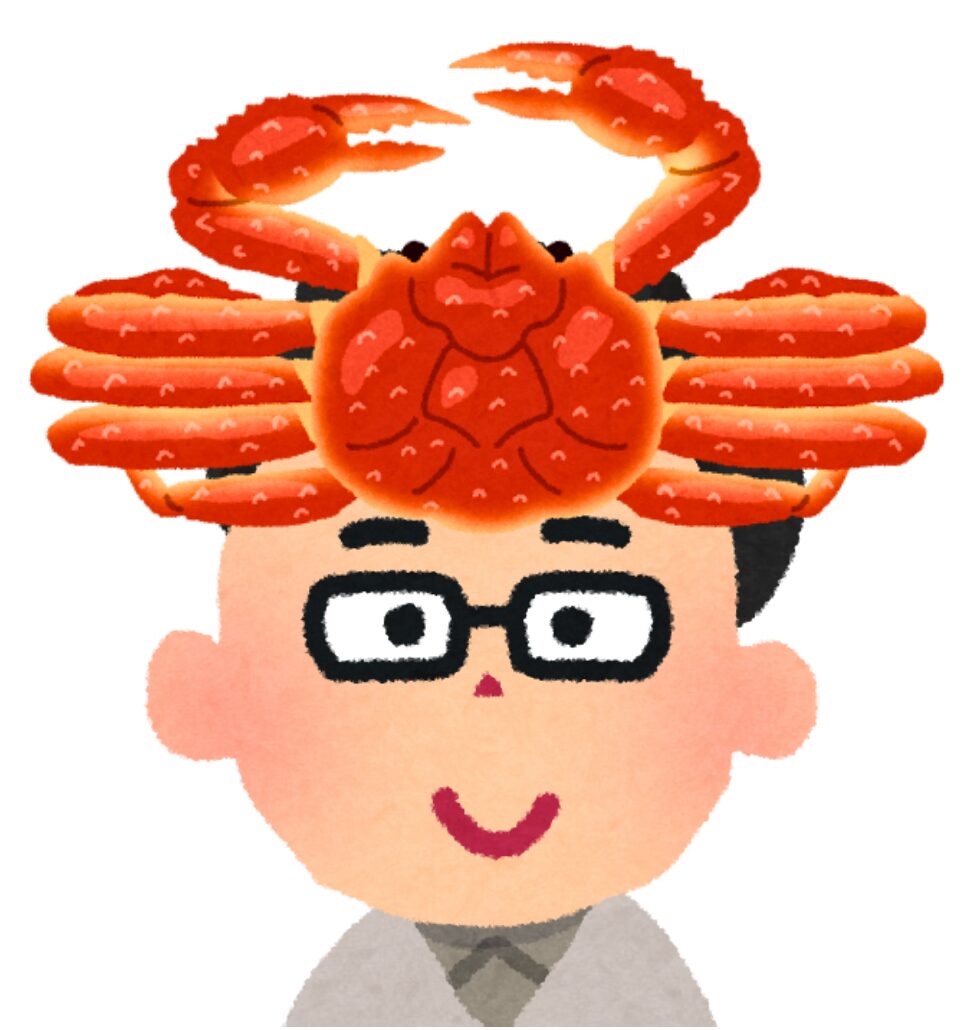
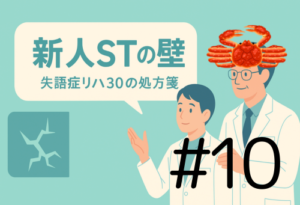







コメント