急性期のリハビリでは、時間も限られ、患者さんの状態も不安定な中で短期目標を立てなければなりません。「とりあえず理解力向上でいいのかな…?」と悩む新人STの声をよく聞きます。今回は、急性期における目標設定の考え方を整理しました。
 ホープくん
ホープくん急性期の患者さんの短期目標として「理解力向上」を設定しようと思うのですが、それでいいんでしょうか?



うん、それも一つの方向性だけど、急性期だからこそ優先したいポイントがあるよ。



優先したいポイント…ですか?



まずは患者さんが「安全に、安定して訓練を受けられる状態かどうか」を目標にするといい。理解力向上はその次の段階だね。



なるほど。じゃあ、急性期の短期目標は安全性や意欲の維持を意識したほうがいいということですね。



そう。さらに、疲労耐性や覚醒レベルの観察も重要。そこが整わないと訓練自体が成立しにくいからね。



理解力の向上ばかりに意識がいっていました…。まずは基盤を整えるのが大切なんですね。



その通り。理解力の目標は、患者さんの状態が落ち着いてきてから設定しても遅くないよ。



ありがとうございます!これからは急性期の特性を踏まえて、現実的な目標を設定します!
急性期では「できる限り早期に言語機能の回復を!」と焦りがちですが、実際には患者さんの全身状態が不安定であることが多く、言語機能訓練がまだ耐えられないケースも少なくありません。
特に以下の要素を重視します:
安全性の確保:訓練が患者さんの体に負担やリスクを与えず、安心して取り組める状態を整える。
覚醒・意識の確認、全身状態の観察、嚥下安全の確認、ポジショニングを確認。
意欲・疲労耐性の維持:患者さんが「やろう」という気持ちを持てるようにし、疲労で悪化しない範囲で続けられる設定にする。
声かけの工夫、課題量と時間の調整、患者の好みを尊重
覚醒レベルの安定:患者さんが眠気や過度の興奮で不安定にならず、訓練に集中できるタイミングを見極める。
タイミングの見極め、環境調整、刺激の調整
理解力向上を目標にするのはもちろん重要ですが、急性期は「まず参加できる状態」をつくり、その中で少しずつ言語刺激を与えるイメージで取り組むと現実的です。
🔑 Key Point|要点整理
- Why:急性期は全身状態が不安定で、言語機能よりもまず「安全で安定して訓練を受けられる基盤づくり」が大切。
- How:
- 安全性(覚醒・嚥下・全身)の評価。
- 意欲や疲労への配慮。
- 簡単な課題で成功体験を積ませ、意欲を高める。
- Tip:急性期は「無理させず、できることから積み重ねる」



あなたは急性期でどのように短期目標を設定していますか?ぜひコメントで教えてください!
📝 Memo|参考資料/書籍
日本脳卒中学会「脳卒中急性期リハビリテーションの指針(2023年5月1日)」



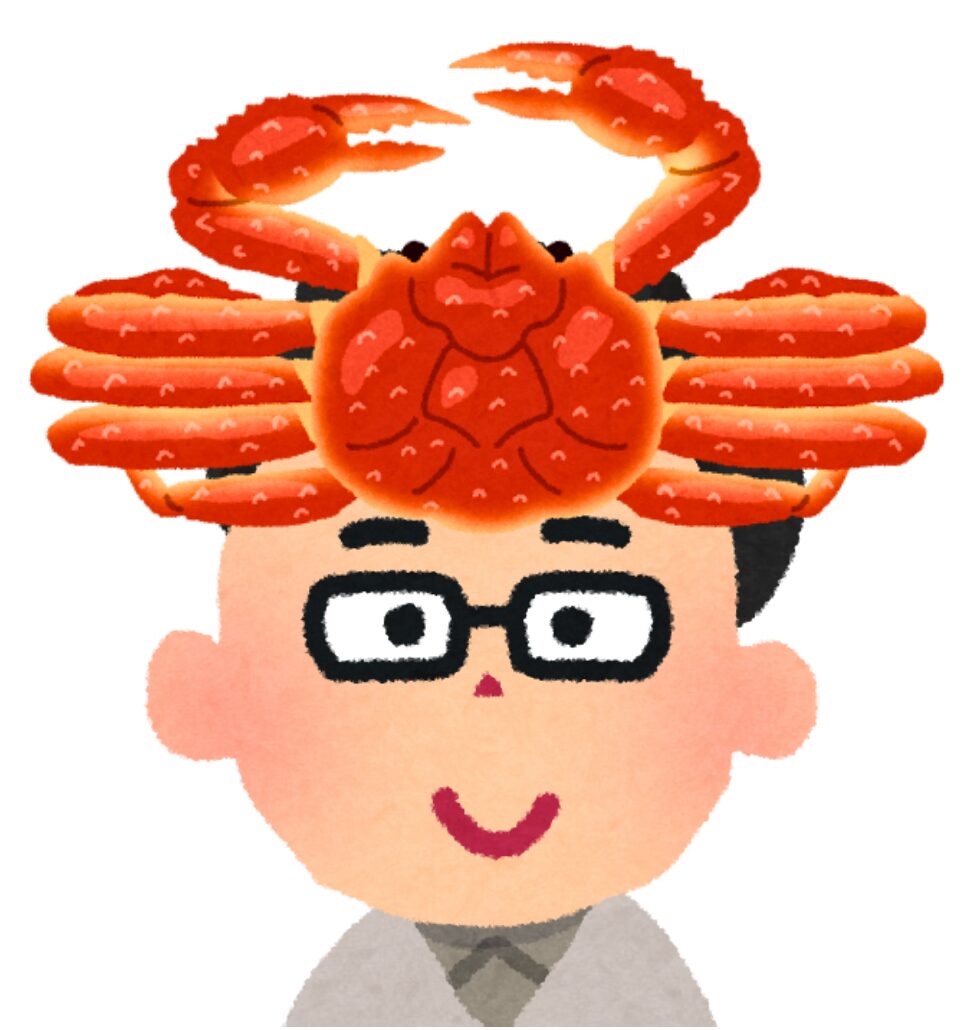
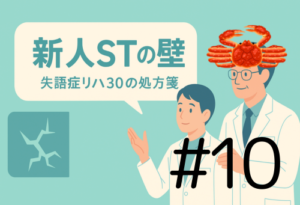







コメント